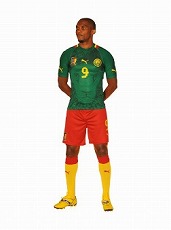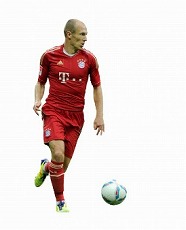今回のサッカー練習のポイント
- 1 【サッカー浮き球処理】今すぐうまくなる3つの手順
- 2 0:24 右足インサイドで少し左側に落として相手をひきつけ逆側へ
- 3 0:59 左足の足裏で一発で前にボールをコントロール
- 4 3:38 素早い胸トラップでの落としからドリブル。落とす角度が参考になります。
- 5 3:58 ももより高い位置のボールを叩き落し、素早く自分のコントロール範囲内に置いている
- 6 サッカー練習メニュー|浮き球がうまく処理できない
- 7 浮き球が処理できないと試合中まごつく
- 8 浮き球処理の練習に最適なリフティング練習
- 9 浮き球処理用、リフティング練習のデメリット
- 10 浮き球処理用、リフティング練習のメリット
- 11 浮き球処理がうまくいかない隠れた原因
- 12 あらためて浮き球処理のためのリフティング練習の【まとめ】
【サッカー浮き球処理】今すぐうまくなる3つの手順
1.浮き球処理を反省する
こんにちは。
まず質問です。
今日もしくは2,3日の間で浮き球の処理時にうまくいかなかった場面を思い出せますか?
思い出せたら、その浮き球の処理の仕方はどうしたらうまくできたのか考えてみましょう。
この「反省」というのがまず一つ目の練習です。
サッカーでは同じ場面は全くないですが、同じような場面はいくらでもあります。
まずは、どうしたらうまくいくのかを考えましょう。
2.つぎは実際にサッカーの試合中に浮き球処理している場面をみる
つぎの練習は浮き球処理の方法を学びます。
1番でうまくできなかった場面を思い出したあなたの頭の中は、「どうすればいいのか?」という気持ちでいっぱいなはずです。
この状態で、いろいろな浮き球処理の場面や練習をみてみましょう。
【必ずヒントがあります】
今回は動画の実例をいくつか紹介するので、
1番でお話ししたように、まずここ2,3日の浮き球処理の失敗の場面を思い出して、考えた後、つぎの動画を見てみてください。
1.サッカー:後ろからくる浮き球ボールの処理例
2.サッカー:多様な浮き球の処理例
3.久保建英選手の浮き球処理例
久保建英選手の浮き球処理です。こちらも多様な場面でうまく相手との関係も意識しながら処理しているのでかなり参考になります。
0:24 右足インサイドで少し左側に落として相手をひきつけ逆側へ
0:59 左足の足裏で一発で前にボールをコントロール
3:38 素早い胸トラップでの落としからドリブル。落とす角度が参考になります。
3:58 ももより高い位置のボールを叩き落し、素早く自分のコントロール範囲内に置いている
どうですか?
いまでは、その効果は分からないと思いますが、きっと明日練習で同じような浮き球くる場面がでてきたときに、同じような処理ができると思います。
はじめはうまくできないかもしれませんが、浮き球の処理はその発想の引き出し、つまりどのように処理するのかをどれだけ多くの種類を過去に見たかにもよります。
今日、これだけの種類の処理方法を見ただけでも明日から変わります。
3.最後は浮き球処理の方法を整理
最後に、浮き球の処理方法を頭の中で再整理しましょう。
頭レベルにきたとき
頭で処理して、つぎはももで処理が多い(メッシのばあい)
⇒これは頭の後、ももで処理することで、短い時間でボールの動きに変化をつけて相手からとられないようにしています。
ももレベルにきたとき
ももで触る場合と、ジャンプして足先で触るパターンがあります。
地面すれすれで触れるとき
時間の余裕があるときは、ボールが地面に触れるくらいのレベルで処理をします。
多くは挟み込むのではなく、クッショントラップをしています。
以上の3つの手順を踏んだだけで、かなり状況はかわります。
『うまい人と練習するとうまくなった記憶はないですか?』
『ワールドカップの試合を見た翌日、うまくなった記憶はないですか?』
そうなんです。
多くの方が経験している方法を応用したのが、この方法です。
わたしは、いまでも新たな処理方法を映像でみるとその週の試合でつかってみることを試みます。
ぜひやってみてください。
そして、このあとは、この方法の大前提となる浮き球の感覚に対する練習を紹介します。
わたしは、浮き球に関しては、映像や実際のプレーを意識してみることが一番だと思っていますが、小学生年代では、リフティングでそもそもの浮き球の感覚を養うこともおすすめしてます。
これは私自身の体験でリフティングをいろいろな形で練習しだしてから、浮き球の処理に対する引き出しと体の動き方のバリエーションが増えて、結果的にうまく浮き球を処理する機会が増えたからです。
以下は、浮き球処理につながるリフティングの練習方法です。リフティングがすでにかなりできている人は飛ばしてもらってよいと思います。
そんな方は、映像をたくさん見ましょう。
サッカー練習メニュー|浮き球がうまく処理できない
浮き球がうまく処理できないって、悩んでいる小学生や初心者の方はいませんか。
そんな方にはリフティングの練習がおすすめです。
なぜなら個人でいつでもできる練習ですし、たとえばアウトサイドなどを使ったリフティング練習をとりいれることで場合によっては試合中にアウトサイドでトラップするという発想もできるようになるからです。
まずは動画を見て一緒に練習してみましょう。
浮き球が処理できないと試合中まごつく
浮き球が試合中にくるとまごついていると、いつまでたってもその次のプレーであるシュートやパスはおろかほっておけば、パスもしてもらえなくなってしまいます。
これって実は小学生や初心者だけのレベルの話ではなくてスピードがあがってくる中学生や高校生でもボールタッチが1cm単位のレベルでうまくできていないと相手のプレッシャーで失敗することなどが頻発します。
なので、1cm単位のレベルでこだわって練習していない人は、
- 浮き球がきてもボールが意図した場所にトラップできない
- プレッシャーが早いチーム相手だと活躍できない
- 体勢がくずれるとうまく処理できない
こうしたことがおきてしまいます。実は、小学生でもやっている練習に浮き球処理を上達させるためのヒントがあるのです。
けっこう、チームでの練習をおもいだしてみてください。結構グラウンダーでボールを扱うことが多くないですか?
その一方で、試合中ってボールがグラウダーのゴロで来ることなんて実はそれほどなくて弾んでいたり浮き球のことが多くないですか?
そうなんです。じつは、試合中には浮き球やバウンドしてくる球がけっこうあるのに、練習ではゴロのパスが多い練習が多いのです。
・パス練習
・3対1や、4対2
・パスを受けてのシュート練習
などなど、思い起こせばゴロのボールでの練習が多いものです。こうしたことを解決してくれるのに意外に最適なのがリフティング練習です。
浮き球処理の練習に最適なリフティング練習
意外に、というか私自身もリフティング練習自体にはそれほどいいイメージをもっていなかったのですが、ただなんとなくやるのではなくて、1cm単位でのボールのあたるところを意識したり、ボールがずれたときの素早い体重移動などを意識するだけでかなりサッカーの浮き球処理の練習にもなっていくのです。
その結果、
- 試合中浮き球がきても落ち着いてさばけるようになる
- ゴロの場合でも1cm単位の精度にこだわれるようになってパスの精度が上がった
- 脚の可動範囲が増えてプレーの幅がひろがった
などといったことができてきます。そうなんです。たかがリフティング練習といえど練習への取り組みの意識を少し変えて、かつメニューをそれなりにするだけで結果もかなりかわってくるのです。
浮き球処理用、リフティング練習のデメリット
とはいえ、リフティング練習にもデメリットはあります。
- 回数にこだわりすぎる
- いつも同じパターンでしか扱えなくなる
- 間違えて覚えると変な癖がつく
こうしたデメリットはちょっとした工夫をすればさけられます。
・回数にこだわりすぎる
⇒100回できるようになったら回数よりもバリエーションを増やすようにすればサッカーの上達に役立ちます。
・いつも同じパターンでしか扱えなくなる
⇒左右、もしくはさわる場所をかえる等すればまんべんなく一通りどこでもボールをあつかえるようになります。
・間違えて覚えると変な癖がつく
⇒動画でうまい選手のマネをしましょう。上達にはまねすることが一番です。
浮き球処理用、リフティング練習のメリット
さて、リフティング練習をすれば「浮き球がうまく処理できない」ひとから、「浮き球をうまく処理できる」ひとに変われます。
しかもリフティング練習のいいところは個人でいくらでも練習できる点です。家のなかですらテニスボールなどをつかえばできますし、雨天でも車庫や庇のしたでプレーが可能です。
だまされたと思って、以下の5つの練習メニューとコツを読んで最後の動画を1週間やってみてください。かなり変わると思います。また、中高生である程度技術のあるひとは、足先のどこにボールがあたっているか1cm単位で意識しましょう。
プロやそれに近いレベルの方はほんとに1cm単位でプレーを評価しています。それくらいこだわれなければ上のレベルにはいけません。どこかで行き詰ります。
たかがリフティングなのですが、浮き球処理の技術を高める個人練習としては最適ですので是非チャレンジしてみてください。
浮き球処理がうまくいかない隠れた原因
浮き球処理がうまくいかない人の中には実は浮き球処理の後のボールの処理の仕方が、うまくなく、敵に取られるということがあります。
これは浮き球処理と、相手からボールを隠すという二つを同時に行おうとするためにうまくいかないのです。
特に、相手からボールを隠すということがうまくできない人は、浮き球の処理がうまくいっても、そのあとがうまくいかないことも多いので結果的に、浮き球が苦手ということになります。
次の動画で、相手からボールを隠す秘訣を確認してみてください。ポイントは、
- 膝を入れる
- 手を使う
この2点です。
あらためて浮き球処理のためのリフティング練習の【まとめ】
1.浮き球を当てる足先の位置
どこにどの角度で当てるかを意識する。
足首は固定するというよりは当たる瞬間にすこし気持ち上にあげる
2.ちょんちょんリフティング
足先を固定しておく練習をするのに便利
軸足の伸縮も重要
常に同じ場所、同じ角度でボールをあてる
3.浮き球を左右交互に1回ずつ、2回ずつ、、、、
軸足を左右ともに鍛える
左右どちらでもボールを当てるポイントは一か所
たとえボールがずれても体をすばやく移動して同じ場所にあてる
4.浮き球を足先、もも、足先、ももを繰り返す
高さのあるところから落ちてくるボールを正確にあつかう
体勢がくずれても同じ場所にあてるようにする
どこに、どのようにあたれば真上にあたるか意識する
5.インサイド⇒足先⇒アウトサイド
とくにアウトサイドはからだの可動範囲を広げることも意識する。インサイドも同様。可動範囲がひろがることでボールをさわれる範囲を広げることを意識する
ということで最後にもう一度動画をみて練習してみましょう!
*最後に練習のコツ。。。
浮き球の練習ひとつとっても、利き足ではじめは徹底的に練習がおすすめ
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
他にも今回このページを訪れた方は、
- サッカーがうまくなりたいけどどうしたらいいかわからない
- 毎日やっていればうまくなる練習メニューはどんなメニュー?
- うまくいかないのは遺伝のせい?
- 上手い人とプレーすればうまくいくと思うけど上手い人が周りにいない
- 浮き球がうまく処理できない
そんな悩みに囲まれているかもしれません。そんなお悩みをお持ちの方は子供サッカー.com の上達マップをみてみてください
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
子供サッカー.com メニュー (いろいろな練習法を紹介してます。)